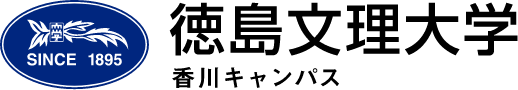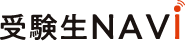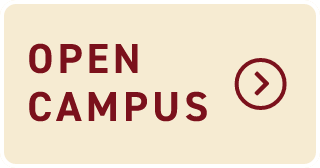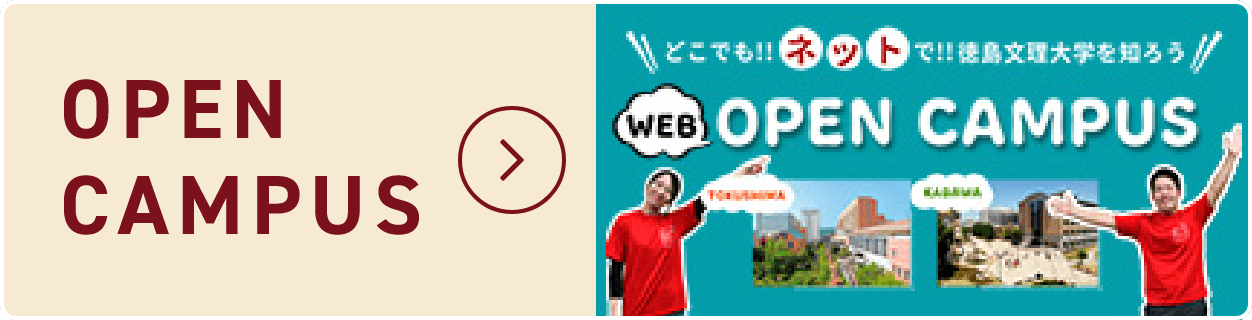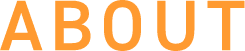比較文化研究所
歴史や文化の調査・研究で
地域文化の振興に貢献
研究について
言語・文学・文化遺産などのもつ独自性、共通性および相互影響に関する研究を実施し、「比較文化研究所年報」にて公表しています。あわせて公開講演会や出張講座を行い地域社会との交流を深める一方、学際的あるいは国際的比較研究も目指しています。

背景と活動

本研究所は、地域文化の振興に貢献することを目的として、昭和58年に設置されました。活動の拠点を文学部内に置き、共同で研究や調査に取り組んでいます。具体的な活動は、以下の通りです。
- (1)言語・文学・文化に関連する調査研究の実施
- (2)「比較文化研究所年報」の発行
- (3)公開講演会および出張講座の開催
- (4)資料の収集整理・保管管理
- スタッフ(2022年度)
- 濱田 宣 研究所所長 文学部長
- 青木 毅 日本文学科 教授
- 古田 昇 文化財学科 教授
- 山本 義浩 英語英米文化学科 講師
主な活動
-
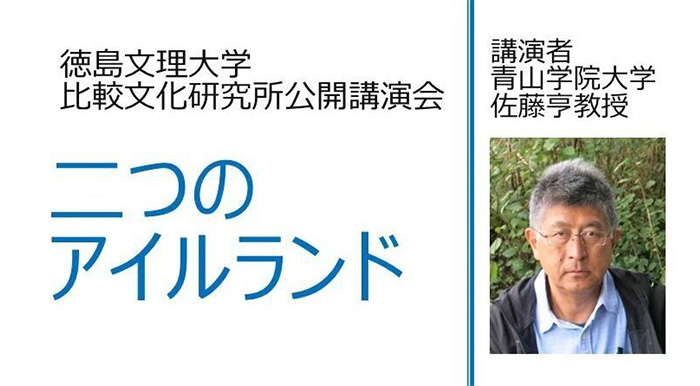
●2021年度公開講演会
「二つのアイルランド」
日時: 2021年10月23日(土) 13時~15時
講師: 青山学院大学教授 佐藤亨先生 -

●2019年度公開講演会 「日本人の美意識」
ー それはなぜ「地味」と「派手」の両極に広がるのか ー
日時: 2019年10月26日(土) 10時~12時
場所: 香川キャンパス図書館3F AVホール
講師: 徳島文理大学文学部教授 立山 善康 氏 -

●講演会 世界を「視る」メディア
-19世紀アメリカ文学から、21世紀インスタグラム映えへ-
日時: 2018年10月20日(土) 13時~15時
場所: 香川キャンパス図書館3F AVホール
講師: フォトグラファー | 文学研究者 別所隆弘 氏
比較文化研究所年報
| 号数 | タイトル | 氏名 |
| 第39号(2023) | 署名されたテクスト─村上春樹「風の歌を聴け」 | 上田穂積 |
| エクリチュールをめぐるテクスト─夏目漱石を受容することの意味 | 上田穂積 | |
| 仏像彫刻の構造・制作技法に関する研究Ⅶ─木造金剛力士立像(広島県福山市・國分寺所蔵)の解体修理記録を通じて─ | 濱田宣 | |
| 弥生時代後期の遍歴する職人たち─香川県原中村遺跡の漆工関係土器類の検討から─ | 大久保徹也 | |
| 精読教材としてのグレイデッド・リーダーズの可能性:Oxford Bookworms版『サイラス・マーナー』を例として | 中島正太 | |
| 文化的景観から地域の自然環境と持続可能な暮らしの知恵を学ぶ | 古田昇 | |
| 令和4年度比較文化研究所展覧会〈概要報告〉 | ||
| 第38号(2022) | 片岡良一と「国際文化振興会」─戦時下の「明治文学会」─ | 中山弘明 |
| 書物,図書館そして廃墟としての〈塔〉─村上春樹「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」再考 | 上田穂積 | |
| 仏像彫刻の構造・制作技法に関する研究Ⅵ─木造金剛力士立像(広島県福山市・國分寺所蔵)の解体修理記録を通じて─ | 濱田宣 | |
| アメリカン・ドリームの光と闇(5)─『ザ・サークル』におけるプライヴァシーの消失とユートピアの行方 | 山本義浩 | |
| 中山間地域の自然環境と文化的景観から考えるESD─徳島県美馬市重清北を例に─ | 古田昇・中条義輝 | |
| 令和3年度比較文化研究所講演会〈講演要旨〉二つのアイルランド | 青山学院大学教授 佐藤亨 | |
| 第37号(2021) | 「1938年」における二枚の〈絵〉―村上春樹「騎士団長殺し」序論 | 上田穂積 |
| 小豆島における未確認石丁場の所在 | 橋詰茂 | |
| 仏像彫刻の構造・制作技法に関する研究Ⅴ―木造金剛力士立像(広島県福山市・國分寺所蔵)の解体修理記録を通じて― | 濱田宣 | |
| 林産資源を利活用した地域振興への協働から学ぶESD―徳島県那賀郡相生地区の杉材を例に― | 古田昇・中条義輝 | |
| 弱々しいロチェスター:映画『ジェイン・エア』(1996)に見るポストコロニアル批評の影響 | 中島正太 | |
| フォークナー、村上春樹、イ・チャンドン―納屋を巡る暴力の諸相 | 山本義浩 | |
| 第36号(2020) | 村上春樹「ダンス・ダンス・ダンス」における〈思想〉―「啓蒙の弁証法」という視座から | 上田穂積 |
| 仏像彫刻の構造・制作技法に関する研究Ⅳ―木造金剛力士立像(広島県福山市・國分寺所蔵)の解体修理記録を通じて― | 濱田宣 | |
| GIS電子地図による吉野川北岸・中山間地の地域調査とESD協働―徳島県三好市西山を例に― | 古田昇・中条義輝 | |
| アダプテーションとしての"Graded Readers"―Penguin Readers版のMiddlemarchを検証する | 中島正太 | |
| 高松城・城下町下層出土の弥生後期土器について | 大久保徹也 | |
| 比較文化研究所公開講演会〈要旨〉日本人の美意識―それはなぜ「地味」と「派手」の両極に広がるのか | 立山善康 | |
| 第35号(2019) | フランクフルトからハンブルクへ―村上春樹『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』の一側面― | 上田穂積 |
| 仏像彫刻の構造技法に関する研究Ⅲ―木造金剛力士立像(広島県福山市・國分寺所蔵)の解体修理記録を通じて― | 濱田宣 | |
| 徳島県那賀町木頭南宇におけるゆず耕作地のGIS可視化から学ぶESD | 古田昇・中条義輝 | |
| アメリカン・ドリームの光と闇(4)―『地球に落ちてきた男』における水のノスタルジア― | 山本義浩 | |
| 「埋蔵文化財」以前の「埋蔵物」管理 | 大久保徹也 | |
| 1950年 快天山古墳発掘調査 | 大久保徹也 | |
| 平成30年度比較文化研究所講演会〈講演要旨〉世界を「視る」メディア―19世紀アメリカ文学から、21世紀インスタグラム映えへ― | フォトグラファー/文学研究者 別所隆弘 | |
| 第34号(2018) | 村上春樹における〈風〉―ユダヤをめぐって | 上田穂積 |
| 仏像彫刻の構造・制作技法に関する研究Ⅱ―木造金剛力士立像(広島県福山市・國分寺所蔵)の解体修理記録を通じて― | 濱田宣 | |
| 文化景観・防災調査で学ぶESD | 古田昇・中条義輝 | |
| 国土測量の基準点標石に採用された香川県小豆島産花崗岩 | 古田昇 | |
| 国府以前のこと 綾北平野における大型石室墳の築造動向とその評価 | 大久保徹也 | |
| 愛媛県域における横穴式石室の型式学的検討―石室諸系統の展開とその特質― | 中嶋美佳 | |
| 公開シンポジウム「身近な歴史遺産の保存・活用とまちづくりを考える」概要報告 | 清水真一 | |
| 第33号(2017) | カントを楽しんで読めますか?―村上春樹「1973年のピンボール」 | 上田穂積 |
| 仏像彫刻の構造・制作技法に関する研究Ⅰ―木造金剛力士立像(広島県福山市・國分寺所蔵)の解体修理を通じて― | 濱田宣 | |
| 新たに確認された綾北平野の大形横穴式石室~坂出市加茂町所在 北山2号墳の横穴式石室とその編年的位置の検討~ | 中嶋美佳 | |
| 埋蔵物録香川県関係資料の基礎的分析 | 大久保徹也 | |
| 〈比較文化研究所公開講座 要旨〉江戸時代小説と近代小説から見た社会風俗と経済 | 元帝京大学大学院教授・現早稲田大学大学院講師 棚橋正博 | |
| 第32号(2016) | 〈引用〉をめぐる断想―村上春樹「風の歌を聴け」 | 上田穂積 |
| アメリカン・ドリームの光と闇(2)―『ナイトクローラー』の夜を巡る欲望― | 山本義浩 | |
| 手続き的公正基準としての一貫性における中学生と大学生との公正知覚の比較 | 原田耕太郎 | |
| 第31号(2015) | 村上春樹における「小島信夫」/小島信夫における「村上春樹」 | 上田穂積 |
| なぜ日本語ではネガティブ・ポライトネスが優勢なのか?―ポライトネスの比較文化試論― | 篠田裕 | |
| ジャック・デリダ:その意味作用、エクリチュール、そして差延をめぐって | Adrian Farrugia | |
| 公開講演会要旨「屋島1934」 | 大久保徹也 | |
| 第30号(2014) | 現代の中国を紹介した本 | 高畑常信 |
| 村上春樹「海辺のカフカ」の構図―折口信夫の形象との関連性から― | 上田穂積 | |
| 『新三十六人歌合』(一首本)とその周辺 | 大伏春美 | |
| 平成25年度比較文化研究所講演会 世界戦争は終わったか?―第一次大戦と日本文学― | 中山弘明 | |
| 『サイラス・マーナー』はいかにして『エピーのねがい』になったのか―ジョージ・エリオットと日本の翻訳児童文学 | 中島正太 | |
| 東洋文庫所蔵梅原考古資料の石清尾山古墳群関係資料について | 大久保徹也 | |
| 第29号(2013) | 論語の名言 | 高畑常信 |
| 村上春樹における〈鳥〉の形象―田村隆一のポエジーとの関連性― | 上田穂積 | |
| 「著」と「着」との区別について―〈節用集〉を中心として― | 青木毅 | |
| 四国南半部エリアにおける弥生・古墳時代遺跡の消長 | 大久保徹也 | |
| ジョージ・エリオットと日本の翻訳児童文学:岡上鈴江訳の『妹マギー』を中心に | 中島正太 | |
| 平成24年度 徳島文理大学 文学部 比較文化研究所講演会(講演概要)『ジェイン・エア』映像化の歴史―「自立する女性」はどのように描かれてきたか | 中島正太 | |
| 第28号(2012) | 鼠と象、あるいは森と平原―大江健三郎と村上春樹 | 上田穂積 |
| 韓国人が見た朝鮮戦争 | 高畑常信 | |
| 共同研究「古墳時代前期の四国島」 はじめに | 大久保徹也 | |
| (報告)津田湾・津田川古墳群の検討 | 大久保徹也 | |
| (報告)阿波東部・吉野川下流域の前期古墳築造状況 | 栗林誠治 | |
| (報告)南四国における前・中期古墳の展開 | 清家章 | |
| (報告)高縄半島における前期古墳の景観と瀬戸内海 | 柴田昌児 | |
| (コメント)「古墳時代前期の四国島」研究会 二日目に参加して | 澤田秀実 | |
| (コメント)伊予における前期前方後円墳築造契機と他地域との関連について | 冨田尚夫 | |
| (コメント)墳墓と集落―研究会「古墳時代前期の四国島」のコメントに代えて | 信里芳紀 | |
| (コメント)前方後円墳築造基盤の変化―高松平野における古墳時代前期の様相から― | 乗松真也 | |
| GIS教育のための環境整備と活用法について | 中条義輝・古田昇 | |
| 公開シンポジウム「津田湾をめぐる古墳群のこれから」概要報告 | 大久保徹也 | |
| 第27号(2011) | 中国の旧社会を描いた林語堂『北京好日』の構成 | 高畑常信 |
| 村上春樹、内田百閒を引用する―「1Q84」への視座、あるいは志賀直哉 | 上田穂積 | |
| 『桃太郎昔語』に対する再考 | 王学鵬 | |
| カフカの『訴訟(プロツェス)』―ある心的過程(プロツェス)― | 井上勉 | |
| 講演要旨「冠婚葬祭から見た韓国社会」講演要旨 | 宋炳五 | |
| 第26号(2010) | 幕末維新期丸亀藩の農村―「諸事日記覚帳」から― | 木原溥幸 |
| 直哉とハルキ―「海辺のカフカ」における一考察 | 上田穂積 | |
| 毛沢東の戦略と人生 | 高畑常信 | |
| 土岐善麿と図書館の歌 | 大伏春美 | |
| 第25号(2009) | 讃岐「生駒騒動」の史料的検討 | 木原溥幸 |
| 〈固有名〉と鼠をめぐる冒険―ハルキと漱石 | 上田穂積 | |
| 四川省夾江千仏岩刻石と造紙博物館 | 高畑常信 | |
| 日韓共同研究へのステップ―所謂〈韓流ブーム〉私見― | 中山弘明 | |
| 平成20年度比較文化研究所公開講演会要旨 | ||
| 第24号(2008) | 頭と子ども―志賀直哉「網走まで」考 | 上田穂積 |
| マルチ人間源内さん | 柳井恒夫 | |
| 高松藩砂糖統制と久米栄左衛門 | 木原溥幸 | |
| 第23号(2007) | ロマ中東起源説 | 井上勉 |
| アメリカ音楽の始まりと発展 | 岡地ナホヒロ | |
| 外国語教育管見―日本語教育海外視察報告を兼ねて― | 篠田裕 | |
| 終助詞「な」の意味再考―話し手の「いま・ここ」における主観的判断の標識として― | 篠田裕 | |
| 「プラーゲ旋風」の波紋―西條八十〈映画主題歌〉と権利問題― | 中山弘明 | |
| 往還する蜂―百閒と直哉 | 上田穂積 | |
| シンポジウム記録「交易する村々」 | 大久保徹也 森下英治 信里芳紀 乗松真也 | |
| 第22号(2006) | 終助詞「な」と「ね」の認識的意味 | 篠田裕 |
| 漱石と勘助―「銀の匙」ノート | 上田穂積 | |
| 日本語教育海外視察報告 | ||
| 第21号(2005) | 映画に見るアメリカ人の行動原理―日本映画との比較より | 岡地ナホヒロ |
| 日本語の助詞「ね」の対人的機能とあいづち―その日本的コミュニケーションスタイルに果たす役割― | 篠田裕 | |
| 〈引用〉の文法―片山恭一の文学趣味 | 上田穂積 | |
| 第4回 公開講演会要旨 | ||
| 第20号(2004) | ヨーロッパ・ロマの起源、種々のロマ・グループ、そして新たなアイデンティティ形成 | 井上勉 |
| 山の神祭り―三重県尾鷲市矢浜地区篝堂、野田地、下地の事例より | 安部剛 | |
| 近代新潟県における割地制―割地視察と伏魔殿― | 青野春水 | |
| 第3回 公開講演会要旨 | ||
| 第19号(2003) | 物語の起源―村上春樹「羊をめぐる冒険」についての一考察 | 上田穂積 |
| エスニック ジョークとイギリスの社会階級―エセックスガール ジョーク | 安部剛 | |
| 近世越後における割地制(六)―束刈割地を中心に― | 青野春水 | |
| 第2回 公開講座要旨 | ||
| 第18号(2002) | 谷崎潤一郎「異端者の悲しみ」異説 | 上田穂積 |
| イギリス小説における「病める語り手」の問題―19世紀を中心に | 中島正太 | |
| 戦争の言語―アメリカ英語におけるイデオロギーの表象 | ジェフリー ハント・安部剛 | |
| 割地制と地租改正―新潟県石津村の場合― | 青野春水 | |
| 〈公開講演要旨〉東アジアのコミュニケーション 歴史と今 女王卑弥呼の外交と瀬戸内海のクニグニ | 石野博信 | |
| 世界の外交・日本の政治~同時多発テロと安全保障~ | 高橋祥起 | |
| 「ことばは何を伝えるのか」~正しいつもりが間違いだらけ~ | 柳井恒夫 | |
| 異文化理解とコミュニケーション―多民族共生時代に向けて | 安部剛 | |
| 日本最初の作品(古事記)にみる国際性と民族性 | 長野一雄 | |
| 他者を動かすコミュニケーション | 原田耕太郎 | |
| 「心の教育」と家庭・地域の人々の役割―情操教育を中心に― | 羽生義正 | |
| 地中からのメッセージ―木簡と讃岐国― | 加藤優 | |
| 片仮名はほんとうに日本人が作ったのか―韓国における角筆の仮名の発見― | 小林芳規 | |
| 江戸時代とは何か―土地制度史よりみる― | 青野春水 | |
| 第17号(2001) | 「剃刀」を巡る覚書―直哉と漱石 | 上田穂積 |
| 近世越後における割地制(四)―「割地竿」を中心に― | 青野春水 | |
| 「逢坂の関のあなた」をめぐって―付「女歌仙」― | 大伏春美 | |
| 第16号(2000) | 島木健作―〈指導〉という装置 | 上田穂積 |
| 近世越後における割地制(二)―地ならしと割地の関係を中心に― | 青野春水 | |
| 「介護」するジャネット―「ジャネットの悔悟」と19世紀イギリスの介護問題― | 中島正太 | |
| ネイティブ アメリカンのエスニック アイデンティティーの考察―Nez Perceインディア(アイダホ州)と都市のインディアン(オハイオ州)の比較より | 安部剛 川村宏明 | |
| 第15号(1999) | 香川県長尾町造田公民館蔵『三體詩』における角筆の書入れについて | 青木毅 |
| 〝母〟の消去、そして引用としての〈物語〉―「きさ子と眞三」の意味と「濁つた頭」 | 上田穂積 | |
| 「円珍伝」の成立について | 加藤優 | |
| 熊本藩の地ならし制について―細川忠利を中心に― | 青野春水 | |
| 文化の概念と異文化間コミュニケーションについて | 安部剛 | |
| 第14号(1998) | 黒島伝治と中村星湖―雑誌「地方」を巡って― | 上田穂積 |
| 『正蒙』譯註―「大易篇」―(その一) | 山根三芳 | |
| 徳島藩の名について | 青野春水 | |
| 日本人の思考様式について―文化人類学的考察 | 安部剛 N.J.C.バサンテク―マー | |
| 第13号(1997) | 追悼文 堀哲先生の思い出のために | 林學 |
| (追悼文)小田真弘先生を悼む | 植苗勝弘 | |
| 日本書紀・続日本紀と日本霊異記―持統紀6年2・3月条、文武紀4年3月条と霊異記上25・22との比較― | 長野一雄 | |
| 安芸中野の小原家伝来の角筆と角筆文献 | 小林芳規 | |
| 徳島藩の壱家・小家について | 青野春水 | |
| 谷秦山の詩(四) | 山根三芳 | |
| 徳島文理大学附属図書館蔵 中條文庫目録 | 小林芳規 青木毅 編 | |
| 第12号(1996) | 広島藩の小村・小村免について | 青野春水 |
| 動詞命令形の機能 | 近藤政行 | |
| SURVIVOR HUMOR IN DISASTERS ―A Comparative Analysis of the Use of Humor in Disasters between Japanese and Americans | 安部剛 サンディ・リッツ | |
| 第11号(1995) | 広島藩(福島正則)の土免について | 青野春水 |
| 谷秦山の詩(三) | 山根三芳 | |
| テレビアニメーション文化の人類学的考察―the Teenage Mutant Ninja Turtlesの事例より― | 安部剛 ジェームズ・マックロード | |
| 第10号(1994) | 中国文学における「憂愁」と古賀侗庵の「愁の賦」(下) | 竹治貞夫 |
| メキシコ・ユカタン半島の民家と遺跡 | 石野博信 | |
| 妙好人庄松 | 井上勉 | |
| 「吉備津の釜」出典小考―温羅伝説をめぐって― | 佐々木亨 原裕一 | |
| アメリカ人類学におけるパラダイムの変化―知識人類学の人類学― | 安部剛 | |
| 日本の宗教的芸能における笑いの機能 | 吉川周平 | |
| 第9号(1992) | 中国文学における「憂愁」と古賀侗庵の「愁の賦」(上) | 竹治貞夫 |
| 桑名における諸職三例 | 堀哲 | |
| 日本の英語教育に対する「日英語の対照研究」の提言的総括 | 織谷馨 | |
| 錬金術と密教―神の子の誕生をめぐって― | 井上勉 | |
| 香川アクセント―若者におこっていること― | 寺川みち子 | |
| 第8号(1991) | 諷刺と笑いをめぐる覚書(4)―瀕死の道化フランソワ・ヴィヨン― | 田島衣子 |
| 異文化コミュニケーションのための外国語教育 | 井上勉 | |
| 日・英語の表現における比較研究(2)―形容詞・副詞・名詞句表現における日・英語の比較― | 八村伸一 | |
| 第7号(1990) | 桂園派歌人近藤忠行 | 兼清正徳 |
| 身体動作の分析と宗教学―アメリカ宗教学会参加への旅― | 吉川周平 | |
| 空海の求聞持法修業による神秘体験の解明―実践カバラーおよびスーフィズムと比較して― | 井上勉 | |
| 諷刺と笑いをめぐる覚書(3)―瀕死の道化フランソワ・ヴィヨン― | 田島衣子 | |
| 日・英語の表現における比較研究(1)―形容詞・副詞句表現における日・英語の比較― | 八村伸一 | |
| 日本語レル・ラレルの韓国語訳 | 朴賢聖 | |
| 第6号(1989) | 桂園派歌人飯尾葛蔭 | 兼清正徳 |
| 中国の鬼〈キ〉と日本の鬼〈おに〉 | 藤原高男 | |
| Thomas carlyle と Jean Paul Richter―Carlyleseの成立をめぐって― | 谷崎隆昭 | |
| 「人」に関する日・英語表現の比較研究(2) | 八村伸一 | |
| 第5号(1988) | 桂園派歌人森川定見 | 兼清正徳 |
| 比較文化と国際教育論 | 吉川周平 | |
| 戦後詩の風景―「荒地」と中桐雅夫の”死〟― | 高柴慎治 | |
| Thomas Carlyle と Edward Irving―その親交について | 谷崎隆昭 | |
| 諷刺と笑いをめぐる覚書(2)―Homo ridens と stultitia crucis― | 田島衣子 | |
| 「人」に関する日・英語表現の比較研究(1) | 八村伸一 | |
| 第4号(1987) | 閨秀歌人鎌田勇子 | 兼清正徳 |
| ”四国の森のなかの谷間の村”訪問―大江健三郎の故郷― | 大伏春美 | |
| Classical and 'Augustan' Notions of the Literary Letter | Wendy Lea Jones | |
| カーライルとシラー | 谷崎隆昭 | |
| Natsume Sōseki and Charlotte Brontë: A Comparative Study | 本間賢史郎 | |
| 日・英語における色彩語の比較研究 | 八村伸一 | |
| カスタネダのドン・フアン・シリーズと比較して見たカフカ―別世界と精霊をめぐって― | 井上勉 | |
| 特集号 日・英語の表現における比較研究 八村伸一 第2号(1986) | Ⅰ 形容詞・副詞句表現における日・英語の比較 | 八村伸一 |
| Ⅱ 動詞表現における日・英語の比較 | ||
| Ⅲ 名詞表現における日・英語の比較 | ||
| 第3号(1986) | 木下幸文の讃岐来遊 | 兼清正徳 |
| 日本語の類義語「きれいだ」「美しい」「麗しい」の異同と中国語「漂(piao)亮(liang)」「美(mei)麗(li)」との対比 | 張徳芬 | |
| トマス・カーライルと国木田独歩について | 谷崎隆昭 | |
| Natsume Sōseki and Nathaniel Hawthorne: A Comparative Study (1) | 本間賢史郎 | |
| Hawthorne and Hardy: 'The World as a Psychological Phenomenon' in The House of the Seven Gables and Tess of the D'Urbervilles | Wendy Lea Jones | |
| 諷刺と笑いをめぐる覚書(1) | 田島衣子 | |
| 関係節の類型論と日本語連体修飾構造 | 寺川みち子 | |
| 日・英語における句読点の比較研究 | 八村伸一 | |
| 特集号 夏目漱石の比較研究 本間賢史郎 第1号(1985) | 『我輩は猫である』とジョナサン・スウィフト『ガリヴァ―旅行記』 | 本間賢史郎 |
| 「幻影の盾」「薤露行」とセオドア・ウオッツ・ダントン『エールウイン』 | ||
| 『坊っちゃん』とジョナサン・スウィフト『ガリヴァー旅行記』 | ||
| 『草枕』とセオドア・ウオッツ・ダントン『エールウイン』 | ||
| 『虞美人草』とジョージ・メレデス『我意の人』 | ||
| 『三四郎』とジョージ・メレデス『我意の人』 | ||
| 『それから』とジョージ・メレデス『リチャード・フェヴァレルの試練』 | ||
| 第2号(1985) | 藤袴の歌―香り・袴と燕姫の故事と― | 大伏春美 |
| 桂園派歌人桜本坊快存 | 兼清正徳 | |
| Eastern Literature through Western Eyes: A Look at Some Modern Japanese Fiction | Wendy Lea Jones | |
| バラのイメージに関する研究―日・英文学における文化的比較考察― | 八村伸一 | |
| 歴史認識としての文学史―人智学的観点から― | 井上勉 | |
| 創刊号(1984) | 文学部建設 | 村崎凡人 |
| 創刊の辞 | 谷崎隆昭 | |
| 書陵部蔵『法華要文百首和哥』翻刻とその解題 | 石川一 | |
| 「和漢名所詩歌合」について | 大伏春美 | |
| 柏原正寿尼宛香川景樹書翰についての研究序章 | 兼清正徳 | |
| Shimazaki Tōson and Thomas Hardy: A Comparative Study | 本間賢史郎 | |
| 目の語彙に関する比較考察―日・英・米文学を中心に― | 八村伸一 |
 その他の情報
その他の情報