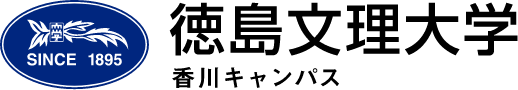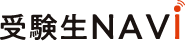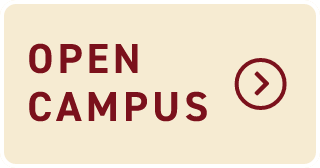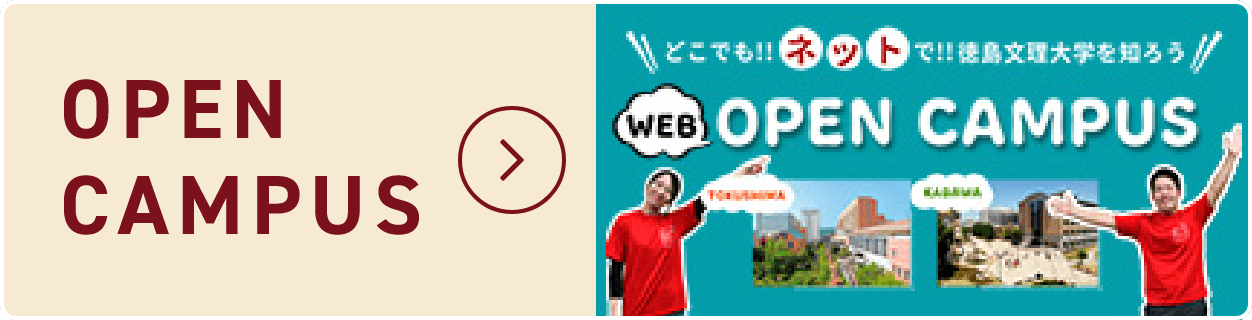研究室紹介・教員一覧
ナノ・バイオテクノロジーの
技術で
社会問題を解決する
科学者・技術者に
ナノ物質工学科では、分子の並び方やつながり方を変えることで新たな機能を持たせた素材を作り出す「ミクロの世界のものづくり」に必要な知識と技術を学びます。工学技術者としてバイオ・医療・農業などの分野で現代社会の問題に挑む人材を育てます。
 教員
教員

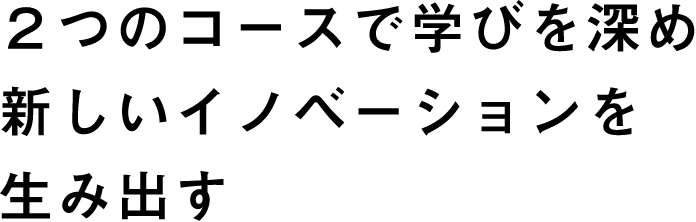
國本 崇材料科学コース 教授
-
ナノ物質工学科ならではの特徴はなんですか?
材料科学コースと生命科学コースの両方があり、これらを合わせた研究ができることです。
一つの例は、梶山研究室が行っているパルスプラズマ光源を用いた新しい植物栽培に関する研究です。梶山研究室を中心に複数の研究室が連携して、それぞれの分野で開発や分析を進めています。
材料科学がメインの國本研究室では、「植物がどのような光をより好んで吸収するか」という性質をもとに、植物の成長に最適な光源を実現するための発光材料の開発を進めており、この光源で使用できる新しい蛍光体を開発しました。
また食品工学を研究している前田研究室ではパルスプラズマ光源で栽培した植物の成分解析を行っており、成長速度以外の観点からこの栽培法の利点を調べています。
このように、材料科学と生命科学を組み合わせると、新しいイノベーションが生まれます。 -
材料科学コースについてお聞かせください。
モノは、決まった性質を持っています。何かモノを作る時は、どの物質の、どんな性質を使って、どんなモノを作っていったらいいか、ということを考えています。
モノの性質を表す最小単位は分子ですが、分子1個のものと、分子100個が集まったものでは、性質が異なります。また、同じ量の分子であっても、並べ方によって性質は違います。
材料科学コースでは、これらの性質の違いを理解し、新しい材料の開発に取り組んでいます。 -
ナノ物質工学科での4年間はどんな内容ですか?
1年生では化学を中心に、物理や生物の基礎を手厚くやっていきます。基礎科学実験など、実験もたくさんあります。2年生の後期から材料科学コースと生命科学コースに分かれ、3年生ではさらに応用的なことを学びます。4年生では学びの集大成としての卒業研究が待っています。
また、これはナノ物質工学科に限った話ではありませんが、徳島文理大学には、学生の疑問や苦手を解消できる教育センターがあります。センターでは、担当の先生が勉強の様々な相談に乗ってくれます。授業でわからないことがあれば、その場で先生に聞いてもいいですし、聞きそびれてしまった場合でも、センターに行けば、担当の先生がじっくり教えてくれます。苦手な科目も克服することができますよ。
 研究室紹介
研究室紹介
研究室紹介(教員一覧)
学科長:箕田 康一
-
ゲノム医科学研究室
がんウイルスによる発がんメカニズム / タンパク質の翻訳後修飾を介した機能変換
- 大島 隆幸
担当授業
化学概論、基礎微生物学、基礎生物化学、分子生物学、技術英語A、生命科学実習B
-
核酸損傷化学研究室
核酸損傷に関する化学的研究
- 喜納 克仁
担当授業
有機化学II、物理化学I、基礎無機化学、無機化学II、技術英語B、物理学A、プロジェクトラボB
-
アグリバイオ研究室
次世代薄膜蓄電でデバイスに関する研究、情報ディスプレイに関する研究
- 梶山 博司
担当授業
基礎物理化学
-
水圏生命科学研究室
魚類および両生類の生殖細胞形成
- 箕田 康一
担当授業
遺伝子工学、生命科学、生命科学実験B
-
ナノ構造科学研究室
発光材料開発とその分光分析
- 佐藤 一石
担当授業
高分子ナノ材料、医用材料工学、材料科学実験
-
フォトニクス材料研究室
ナノテクノロジーに欠かせない、ナノ粒子、電子材料等さまざまな技術展開を学びます。
- 國本 崇
担当授業
先端材料、分析化学、プログラミング演習
-
応用生物工学チーム
バイオ生産研究室微生物を利用した有用物質の生産とその利用
- 文谷 政憲
担当授業
バイオテクノロジー入門、基礎生物化学、生命科学実験A
-
アグリバイオ研究室
新規可食性化合物の合成
- 前田 淳史
担当授業
応用微生物学、酵素工学、基礎有機化学
-
アグリバイオ研究室
- 谷川 浩司