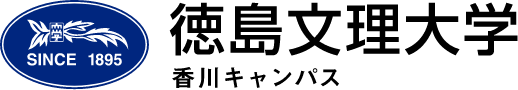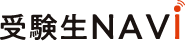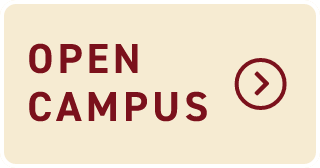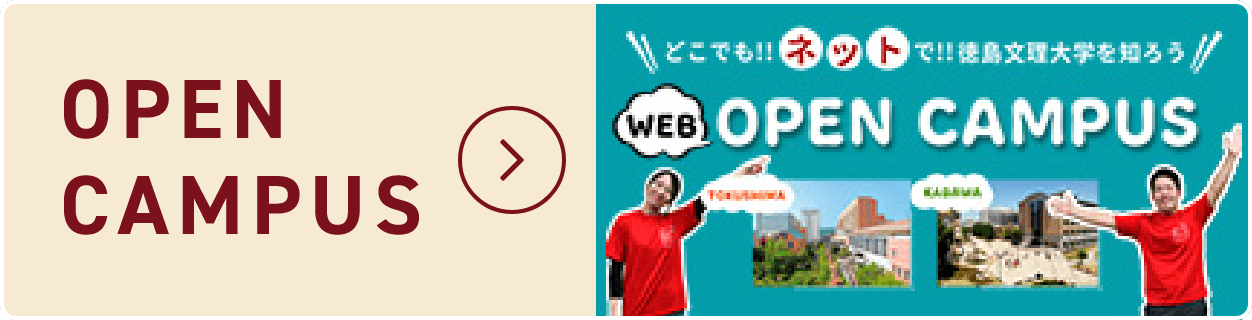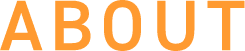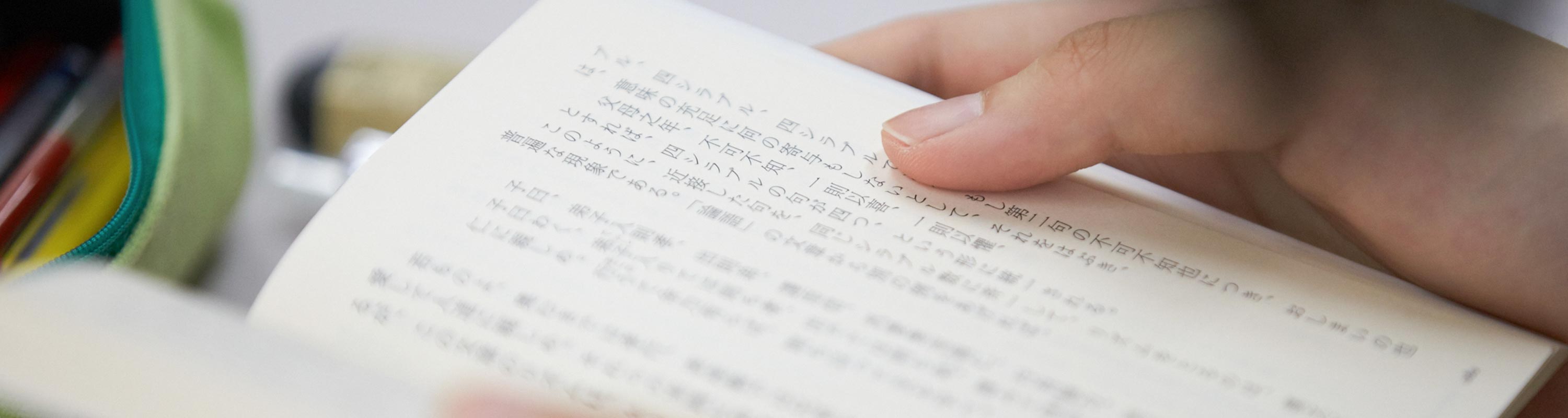
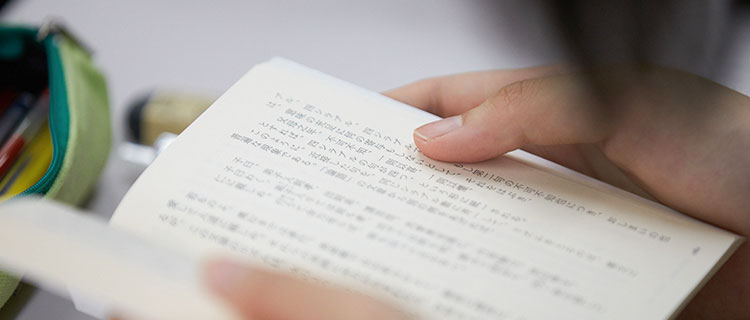
日本語史
言葉はなぜ変化するのでしょうか。この授業では、日本語史上に生じたさまざまな変化について、その原因を明らかにしていきます。
教授青木 毅
 授業・研究について
授業・研究について
■授業について
「日本語の乱れ」が叫ばれる昨今ですが、日本語の乱れを嘆く人というのは、いつの時代にもいたと思われます。平安時代の清少納言(『枕草子』の作者)や鎌倉時代の兼好法師(『徒然草』の作者)も、自分の作品の中で、今どきの言葉遣いについて苦言を呈しています。言葉はなぜ変化するのでしょうか。この授業では、日本語史上に生じたさまざまな変化について、その原因を明らかにしていきます。
【上記以外の主な担当科目】
- 「日本語文法概説」
- 『徒然草』をテキストとして用い、文法事項を説明しながら、内容を読み解いていきます。
- 「日本語音声学」
- 日本語の発音のしくみについて学ぶことで、発音に関するさまざまな現象について解説します。
- 「日本語の文体」
- 日本語では漢字・平仮名・片仮名を使い分けていますが、その理由を、文体の発達と関連させながら解き明かしていきます。
■研究について
本研究室では、日本語を使うことの難しさや奥深さ、言葉というものの不思議さを日々感じながら、研究したり授業の教材を吟味したりしています。
正しい日本語とは何なのでしょうか。
実は、普遍的に正しいと言える日本語は、どこにも存在しません。
そうかと言って、どんな言葉遣いでもOKというわけではありません。
日本語の歴史を学ぶことによって、日本語の奥深さを知り、ふだん無意識に使っている日本語を見つめ直しましょう。
 講師の紹介
講師の紹介


教授青木 毅
担当授業
- 日本語史
-
研究室名
日本語学研究室
中高生への
メッセージ
コミュニケーション能力が求められる昨今ですが、コミュニケーションというと、発信する側の技術(上手に話せること、分かりやすい文章が書けること)をまずは思い浮かべると思います。
しかし、受信する側の技術(話を正確に聞き取ること、文章を正確に読めること)も大事です。
コミュニケーションとは、相手の"声"に"耳を傾ける"ことから始まるのだと思います。
 その他の情報
その他の情報