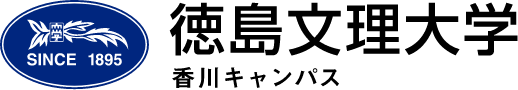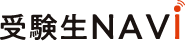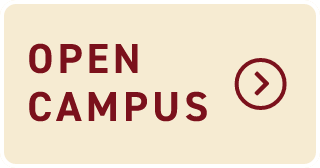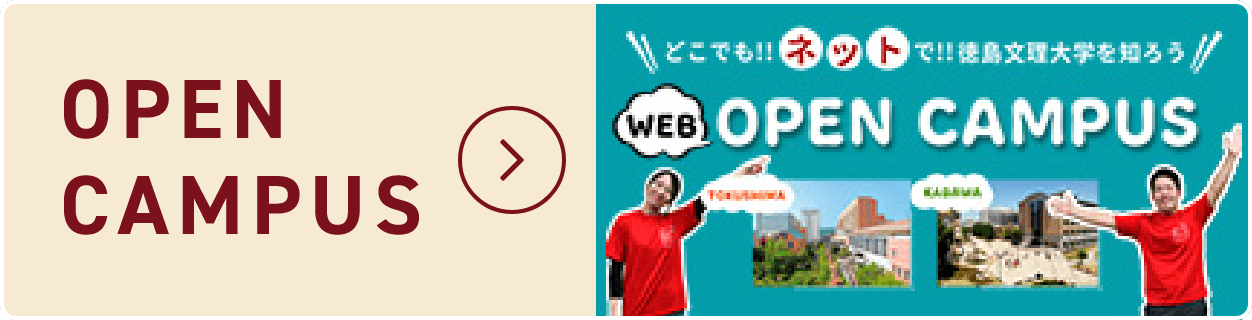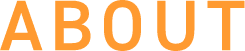大学院文学研究科
言語、文学作品、歴史遺産の研究を通して
それらを現代社会に位置付けます。
言語・文学と地域
- 研究者となるための不可欠な知識を
修得。 
- 日本語学と英語学、日本文学と英米文学の各分野において、大学院生の専門に応じた徹底的な個人指導がなされます。研究者となるための不可欠な知識を修得することにとどまらず、専攻分野における自分の研究が占める位置やその独創性も検証することになります。客観的な研究態度や方法の獲得は、自らを大きく成長させてくれるでしょう。
文化と地域
- 文化財にかかわることのできる人材、時代が求める人材を育成。

- 地域文化、特に瀬戸内地域はかつて、国内および国際的な海上交流の舞台でした。現在、これまでに修得した知識、技術を駆使して他大学などと共同研究を行っている「尾道の中世寺院の調査研究-西國寺の歴史と文化」は、今後も大きな歴史的な発見が期待されています。このほかにも、眠っている地域文化遺産の共同研究は、ますます広がっていく傾向にあります。未来を見据える視座としての文化財にかかわることのできる人材、そんな時代が求める人材を育成したいと考えています。
 概要
概要
文学、言語学、考古学、歴史学、文化史学、地理学などの教授研究を行い、地域文化の継承と創造的発展に寄与しうる探究心と学問的客観性を体得した人材を養成します。
前期課程2年で修士(文学)、後期課程3年で博士(文学)を取得

- 取得できる資格
- 高等学校教諭専修免許(国語・英語・地理歴史)、
中学校教諭専修免許(国語・英語・社会)
※ただし、それぞれ高等学校教諭一種免許または中学校教諭一種免許を有するものに限る。 - めざせる進路
- 教育職、研究職、そのほか高度の学識を必要とする専門職
 研究テーマ
研究テーマ
- 博士論文
- 大和弥生文化の特質
- 日本近世小説における挿絵の効力について -『世間娘気質』と『滑稽冨士詣』を中心に-
- 横穴式石室の築造動向からみる地域秩序の形成過程とその評価―四国諸地域を中心に―
- 修士論文
- 南四国における横穴式石室墳築造の定着過程 -石室の型式分類と編年を中心に-
- 村落における宗教景観と山岳信仰 -松山平野および周桑・西条平野を事例として-
- 明治初頭の国字表記を巡って
- 仏教絵画における四天王図像の形態比較
- 安宅信康と淡路国衆 -十六世紀後半における東瀬戸内地域の国人に関する一考察-
- 鎌倉時代の「三尺阿弥陀如来立像」の作風展開について
- 飛鳥・奈良時代における死生観の基礎的考察
- English Education in Japan
- Circumstances of the World Using English and Necessity of English in Japan- - 普賢菩薩、文殊菩薩の図像
- 公民権運動における黒人音楽 -ラグタイムとジャズのたくましい力を明らかにする-
- 不動明王の像容に関する考察 -「弘法大師様」・「円珍請来様」を中心に-
- 「スポーツ」・「文学」・「資本主義」 W.Pキンセラー『シューレス・ジョー』より トニ・モリスンBelovedにおける登場人物の心理
- 八月の光におけるウィリアムフォークナーの女性像
- 山頭火における良寛 ―深化の十年をめぐって―
- 近世紀から明治初期の絵本『猿蟹合戦』について―「海幸山幸神話」との共通性の観点から―
- 文学作品における修辞的言語『マルタの鷹』の翻訳をめぐって
- 『竹取物語』の研究―「親子の情」より「孝」に及ぶ―
- 中世後期土佐一条氏の港津支配に関する研究
- Jane Austenの小説におけるFormalityとFreedom
 その他の情報
その他の情報